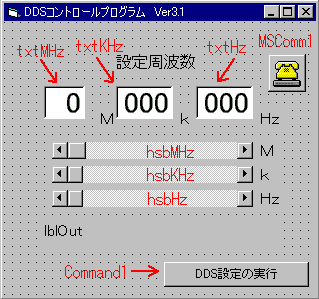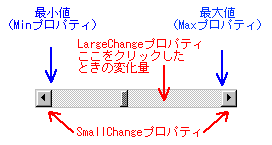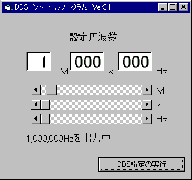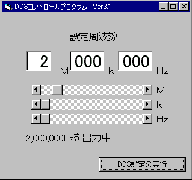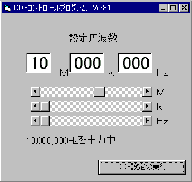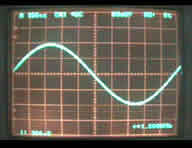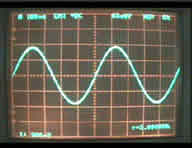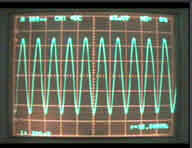;***********************************************************
; DDSコントロール・プログラム3
;【 動作内容 】
; PICリセット後、確認のため PORTB の LED が1秒間点灯する。
; パソコンからのデータは、
; チップセレクトデータ(3ビット)
; コマンドデータ(4ビット)及び
; 周波数データ(24ビット)
; を、RS232C シリアル通信で送る。
; 周波数データは、下位から4ビットずつ区切って6分割し、
; 下位から順に、分割したデータとして送る。
; 各データはバッファに一時格納し、データの受信が完了したら、
; 随時、DDS 設定信号を出力する。
;
;【 DDS 接続ポート 】
; (DDS) (PIC)
; STB ………RE0
; DATA………RE1
; SCK ………RE2
;
;【 RS-232C 接続ポート 】
; 非同期式通信モード
; ボーレート 9600bps
; 8ビット・ノンパリティ
; 割り込みは使用しない
;
;***********************************************************
|
LIST P=PIC16F877
INCLUDE P16F877.INC
|
;(1)プロセッサの種別指定
;(2)インクルードファイルの指定 |
;***********************************************************
; 変数定義とレジスタ割付
;***********************************************************
|
COUNT EQU 20H
COUNT1 EQU 21H
COUNT2 EQU 22H
COUNT3 EQU 23H
COUNT4 EQU 24H
TEMP EQU 25H
COUNT_D EQU 26H
COUNT_S EQU 27H
|
;(3)ループカウンタ
; ループカウンタ1
; ループカウンタ2
; ループカウンタ3
; ループカウンタ4
; 一時保管データ
; データカウンタ
; シフトカウンタ
|
;***********************************************************
; 初期化
; (注)バンクの位置に注意
;***********************************************************
|
ORG 0
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000010'
MOVWF ADCON1
CLRF TRISE
CLRF TRISB
MOVLW B'10111111'
MOVWF TRISC
MOVLW B'00100100'
MOVWF TXSTA
MOVLW 81H
MOVWF SPBRG
BCF STATUS,RP0
MOVLW B'10010000'
MOVWF RCSTA
|
;(4)プログラムの開始番地の指定
;(5)Bank 1 へ切替
;(6)RE0,RE1,RE2 デジタル入出力
; ADCON1レジスタの設定
;(7)PORTE 全ポートを出力に設定
;(8)PORTB 全ポートを出力に設定
;(9)RC7/RX(入力),RC6/TX(出力)
;(10)PORTC の設定
;(11)8BIT,送信許可,非同期,高速
; TXSTA レジスタの設定
;(12)ボーレート 9600bps (20MHz:高速設定時)
; SPBRG レジスタの設定
;(13)Bank 0 へ戻す
;(14)シリアル,8BIT,継続受信許可
; RCSTA レジスタの設定
|
;***********************************************************
; メインプログラム
;***********************************************************
|
MOVLW B'00000111'
MOVWF PORTE
MAIN
BSF STATUS,IRP
MOVLW 0A0H
MOVWF FSR
MOVLW 8H
MOVWF COUNT_D
|
;(15)DDS信号ラインのレベルの初期設定
; SCK,DATA,STB = [H],[H],[H] に設定
; PORTEへ出力(DDSとの通信の初期設定)
;(16)間接アドレス設定
; バッファの先頭アドレスをセットする
; 間接アドレスポインタの初期化
;(17)8回繰り返す(DDS設定データ)
; データカウンタのセット
|
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
CALL TIME1S
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
|
;(18)データ受信待ちになっていることを確認するためのLED表示
; 11111111 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの点灯)
;(19)1秒のウエイトを入れる
;(20)00000000 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの消灯)
|
LPRCV
BTFSS PIR1,RCIF
GOTO LPRCV
|
;(21)USART 受信割り込みフラグビットのチェック
; PIR1 レジスタの RCIF が「0」だったら
; LPRCV ラベル間をループする
|
BTFSC RCSTA,FERR
GOTO FRAME
BTFSC RCSTA,OERR
GOTO OVER
|
; ****** エラーチェック ******
;(22)フレーミングエラーのチェック(1:エラー,0:正常)
; フレーミングエラー時 FRAME のラベルへジャンプする
;
;(23)オーバーランエラーのチェック(1:エラー,0:正常)
; オーバーランエラー時 OVER のラベルへジャンプする
|
MOVF RCREG,W
MOVWF INDF
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT_D,F
GOTO LPRCV
MOVLW 0
MOVWF INDF
|
; ****** 受信データの格納 ******
;(24)RCREGレジスタから受信データを読み込む
;(25)バッファに格納
;(26)ポインタ +1
;(27)データカウンタ −1
; LPRCV のラベルへ戻り繰り返す
;(28)25,24ビット目のDDS周波数データ(常に0)
; バッファに格納
|
DDS
MOVLW 0A0H
MOVWF FSR
MOVLW 9H
MOVWF COUNT_D
|
; ****** 格納データの取りだし ******
;(29)バッファの先頭アドレスをセットする
; 間接アドレスポインタをリセットする
;(30)9回繰り返す(DDS設定データ)
; データカウンタのセット
|
DDS_SET
MOVF INDF,W
MOVWF TEMP
MOVF COUNT_D,W
CALL TABLE
MOVWF COUNT_S
|
;(31)バッファに格納されているデータをWregにロードする
; 一時保管データへ
;(32)データカウンタの値をWregへロードする(OFFSET)
;(33)シフトカウンタ値の読み込みサブルーチンへ
;(34)シフトカウンタのセット
|
DDS_LP
RRF TEMP,F
BTFSS STATUS,C
GOTO DATA_L
GOTO DATA_H
|
;(35)DDS設定データを取り出す。
;(36)データが1だったら次の命令をスキップ
; DATA = [L]
; DATA = [H]
|
SET_SCK
BCF PORTE,2
NOP
BSF PORTE,2
DECFSZ COUNT_S,F
GOTO DDS_LP
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT_D,F
GOTO DDS_SET
|
;(37)SCK = [L]
;(38)ポートの誤動作防止
;(39)SCK = [H]
;(40)シフトカウンタ −1
; DDS_LP のラベルへ戻り繰り返す
;(41)間接アドレスポインタ +1
;(42)データカウンタ −1
; DDS_SET のラベルへ戻り繰り返す
|
BSF PORTE,1
NOP
BCF PORTE,0
NOP
BSF PORTE,0
GOTO MAIN
|
;(43)DATA = [H]
;(44)ポートの誤動作防止
;(45)STB = [L]
;(46)ポートの誤動作防止
;(47)STB = [H]
;(48)繰り返しデータ受信動作に入る
|
DATA_L
BCF PORTE,1
GOTO SET_SCK
DATA_H
BSF PORTE,1
GOTO SET_SCK
|
;(49)DATA = [L]
;(50)DATA = [H]
|
;***********************************************************
; シフトカウンタ・テーブル
;***********************************************************
|
TABLE
ADDWF PCL,F
NOP
DT 2,4,4,4,4,4,4,4,3 |
;(51)TABLEの定義(PC+OFFSET相当のシフトカウンタ値を持って戻る)
; PC+OFFSET
;(52)ダミーデータ
;(53)各データに対するシフトカウンタ値 |
;***********************************************************
; RS232Cシリアル通信エラー時の処理
;***********************************************************
|
FRAME
MOVLW B'00001111'
MOVWF PORTB
CALL TIME1S
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
MOVF RCREG,W
BTFSS RCSTA,OERR
GOTO MAIN
|
; <フレーミングエラー時の処理>
;(54)00001111 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの点灯状態でエラーを知らせる)
;(55)1秒のウエイトを入れる
;(56)00000000 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの消灯)
;(57)ダミーの入力とFERRフラグをリセット(RCREGをリードするとクリア)
;(58)オーバーランエラーのチェック(1:エラー,0:正常)
; オーバーランエラーがなければ MAIN のラベルへジャンプする
|
OVER
MOVLW B'11110000'
MOVWF PORTB
CALL TIME1S
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
BCF RCSTA,CREN
BSF RCSTA,CREN
GOTO MAIN
|
; <オーバーランエラー時の処理>
;(59)11110000 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの点灯状態でエラーを知らせる)
;(60)1秒のウエイトを入れる
;(61)00000000 を Wreg にロードする
; PORTBへWregのデータを出力(LEDの消灯)
;(62)OERRのリセット(ビットCREN のクリアによりクリアする)
;(63)連続受信を許可する
;(64)MAIN のラベルへジャンプする
|
;***********************************************************
;遅延サブルーチン
;***********************************************************
;100μs遅延サブルーチン(20MHzクロック時)
;・・・・・別記プログラムリスト参照・・・・・
;
;10ms遅延サブルーチン(20MHzクロック時)
;・・・・・別記プログラムリスト参照・・・・・
;
;1s遅延サブルーチン(20MHzクロック時)
;・・・・・別記プログラムリスト参照・・・・・
|
END
|
|